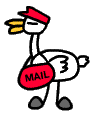
| 木のつぶやき | 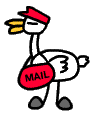 |
| 2006年01月03日(水)晴れ |
2005年を振り返って
| <1月>ダイエットがなぁ… |
| お正月早々3日に名古屋の伯母が亡くなり4日に日帰りで名古屋まで出かけている。毎年お正月には気合いの入った目標をノートに書き付けている。2005年は(1)社労士通信講座→期限ギリギリでかろうじて提出、(2)士一次試験の勉強→くじけた、でも茨城県手話通訳士養成講座、また谷和原村手話奉仕員フォローアップ講座の講師担当を通じて自分なりに頑張れたかなという気がします。(3)体重70キロを切る→全然ダメ(>_<)。年末に「ほぼ日手帳」買っていろいろ「やりたいこと」を書き留めてるんですけどねぇ〜。わっ、交通違反をして罰金も払ってる。次女の私立高入試もあった。台風で屋根瓦の一部が浮き上がった修理もしてるし、携帯もAuに換えてるなぁ。おっと、27日に長女の「父兄召還」で高校へ行って教頭先生に頭を下げてる…(-_-;)波乱の1月スタートでした。 |
| <2月>ブログ三昧…? |
| 9日にサッカーのワールドカップ・アジア最終予選・北朝鮮戦があり、日本代表は大黒の劇的ゴールで勝利、メッチャ感動した。その反動でもないが風邪で3日間も会社を休んだ。そのくせ28日に国リハの卒論発表会を見に行ったりしている。一昨年教官面接試験を受けて以来の国リハだった。1月の末にブログを始めて2月はちょっとブログにはまってそれ以外の活動がお休み状態。 |
| <3月>それなりに頑張ってたのですが… |
| 3日に次女の県立入試があり、1日には湯島天神に行った。今年は三女の入試だからまたお世話にならなければ…。7日は「おはよう茨城」の手話通訳ビデオ撮り。12日には第5回日本手話教育研究大会に参加。19日には通研の討論集会報告会にも参加、このときは水戸までバイクで行って死ぬほど寒かった。21日には新横浜で行われた「手話通訳と人権」集会にも参加。それなりに気合い入っていたのですが、26日に技短の長谷川先生退官記念パネルディスカッションの通訳で落ち込んで以来かなりメゲました。31日手話通訳士に新たに2名合格、かつて担当した手話通訳者養成の受講生だったので大変嬉しかった。 |
| <4月>ほぼ日手帳も挫折… |
| 10日に伊藤政雄さんの講演会。24日には石川芳郎さんの障害者自立支援法に関する講演会もあった。いずれもとても勉強になった。14日に谷和原村手話サークル・フレンズの例会に参加、今年は毎回参加しようと思っていたのだが、なかなかさんかできなかった。今年こそは頑張りたい。正月以来ずっとお金がなくて、手帳に細かいお金の使途が書き留めてある。労金のカードローンでなんとかやりくりしている状態だった。連休前、半年ぶりに散髪に行けた。頑張って書いてきた「ほぼ日手帳」はこの時期に挫折。 |
| <5月>謎のゴールデンウィーク… |
| 19日に谷和原村の手話奉仕員養成フォローアップ講座で使用する教材用のビデオ撮影を敢行。集まってくれたのは結局講師以外は1名だったのですが、初めてのオリジナル・ビデオ教材製作でした。なぜかゴールデンウィークに何をしたのか全然記録が見あたらない。2日と6日休みをとって10連休したはずなんだけど…いったい何をしていたのだろうか僕は…。26日に谷和原村の手話奉仕員養成フォローアップ講座が始まった。 思い出した、GWは社労士の通信講座を一気に片付けてたんだった(^_^;)>。 手帳には書いてなかったけど、5月にはHDD&DVDレコーダー(東芝RD−XS36)を49,800円で購入してた。士養成講座の準備にどうしても欲しかった機材。これで教材ビデオをDVD化できる環境が整った! |
| <6月>2年連続で通訳者養成講座の講義「手話通訳者の理念と仕事」を担当 |
| 6月には茨城県手話通訳士養成講座の準備が始まった。5月末申し込み締め切りで4日に書類選考を行った。一方で6日に「おはよう茨城」手話通訳ビデオ収録、18日には手話通訳者養成講座の水戸会場を見学、19日には教材用のろう者手話ビデオ撮影を守谷で行った。25日(土)は手話通訳者養成講座で「手話通訳の理念と仕事」をテーマに講演、26日(日)は通研の講演会で「障害者自立支援法」について話しをさせてもらった(レジュメは過去の資料の寄せ集めで紙ベースで作ったもののみ→いずれホームページにアップしなければと思いつつ今日までサボってきてしまっている。)。29日(水)には通訳者研修会を担当した。月末は徹夜も含めて一気にやった感じでした。 |
| <7月>けっこうエネルギッシュでした |
| 三女が受験なので勉強部屋にクーラーを購入、ところが次女の部屋のクーラーもぶっこわれて、泣く泣く2台買い換える羽目に…。ボーナスがぶっとんだ(-_-;)。 4日に守谷市の手話講習会を見学させてもらい、25日に「手話を通じた市民活動」というテーマで話しをさせてもらった。9日に士養成講座の説明会を読み取りと聞き取り表現のビデオ撮りも兼ねて行った。撮ったビデオは後日DVDに焼いて受講生に配布、講座が始まる9月までに事前に自己チェックしておいてもらうことにした。同じ9日には県西の学習会に参加し「障害者自立支援法」について話しをさせてもらった。翌10日は筑波大学でノートテイカー養成講座の手話通訳。ホントは同日に行われた越智さんの講演会「障害者自立支援法」を聞きたかった。16日には士養成講座の読み取り教材としてろう者のビデオ撮影をさせてもらった。なかなか良い教材ができたと思う。22日には義兄のミッシェルさんが仕事で来日、筑波でお会いできた。翌23日には母が東光合唱団の発表会を聞きに上京、帰り際大きな地震があって地下鉄が止まり、蛎殻町の日本橋公会堂から東京駅まで歩いた。そして24日には長女の専門学校見学に付き合った。さらに30日には通訳者研修の手伝いもやって、7月はなかなか頑張ってました。 |
| <8月>帰省もしなかったのに、何もしてなかった…? |
| 去年に続き9日に阿字ヶ浦へ海水浴に、といっても次女のアッシー君なんですが。8月24日にはつくばエクスプレスが開通。29日に娘3人と富士急ハイランドで一日遊んだ。8月は恐らく士養成講座の準備をしてたはずなんですが、手帳には特になにも書いてなくて、思い出せない。6月後半から7月に頑張った反動かな…。 |
| <9月>申し込み忘れて関東ろうあ青年の集いに参加できず… |
| 3日に士養成講座が開講、とりあえず担当は第4回以降だけど心配だし機材のチェックもしたかったので参加。17日は手話通訳、長崎原爆60周年記念チャリティコンサートでした。そうかもう戦後60年なんだね。23日から2泊3日で「関東ろうあ青年の集い」が茨城であったのですが、協力員申し込みの文書を出し忘れて参加できなかった。こういう肝心なときにチョンボで不参加なんだよねぇ〜僕は、ホント役立たずだよ。 |
| <10月>士養成講座に必死… |
| 1日、8日は士養成講座の読み取りパートだった。担当ではないけれど受講生の様子を知りたくて参加。15日にいよいよ自分が担当する聞き取り表現パートがスタートした。とりあえずは順調な滑り出し、是非合格へ向けて力になりたかった。23日には通研のつどいに参加、手話サークル分科会に参加したがあまりの参加者の少なさに驚いた。う〜んこれではいかんよなぁ〜。30日は通訳者研修会、要約筆記者との合同研修だった。「読み取り通訳者の明らかな読み違いを要約筆記者が勝手に修正してもよいかどうか」で議論になってなかなか面白い研修会だった。私は情報を受け取るろう者の利益を考え、直せるものは直すという立場。 |
| <11月>頸肩腕ストレッチの覚え方をみんなで考案! |
| 5日、12日と士養成講座の聞き取りパートの担当があり、その後19日には模擬試験を実施、そして27日が士試験本番だった。みんなが実力を発揮できたことを信じている。必ず合格できると信じている。みんなそれだけの努力をしたと思う。 13日には東京で士協会の研修会があって茨城から7名が参加、大変勉強になった。こうして仲間と共に参加することの意義はとても大きい。早速25日の通訳者研修会・事例検討で、研修を受けた「警察での通訳」について参加者に話しをしてもらい大変好評だった。 30日には久しぶりに筑波技術大学で遠隔地手話通訳実験のお手伝い、そして夜は通研県南地域班の集まりに参加、ケイワンストレッチの振り付けをやった。何と去年のこの欄に「前から思っていたのですが、頸腕ストレッチに音と歌詞をつけてラジオ体操みたいにできたらいいのになぁ〜。」と書いていたのを1年後に実現できた。音は付けてないけど、リズムを付けて語呂合わせでストレッチを覚える方法をみんなで相談してまとめたのだ。 |
| <12月>最後まで勢いが出ないまま終わってしまった |
| 2日に守谷市で手話通訳派遣制度についての勉強会があり参加、その日の夜中出発で3日に名古屋で行われた祖母の法事に参加、とんぼ返りで茨城に戻って、4日には古河市での日曜教室・小海さん講演「障害者自立支援法」を聞いた。8日は谷和原の手話サークル・フレンズの忘年会があった。11日にはつくばで日曜教室「日本手話について」があり江戸川区ろう協の中山さんのお話しを聞かせてもらった。 12〜13日と人間ドックに入って「食事を控えましょう」と指摘された。17日(土)には通訳者研修会・読み取りがあり、午後は来年に備えて通訳者養成講座を見学。18日には士グループの集まりもあった。22日の谷和原村手話奉仕員フォローアップ講座が手話関係の活動納めになった。まあまあ今年は頑張ったかな。 |
2004年を振り返った時にはこの欄で「最低限の『職業としての手話通訳者制度』を確立する手だてを現実的に考えていかなければならないのではないだろうか。」と書いている。2005年は総選挙における自民党圧勝を受け、障害者自立支援法も一気に成立、手話通訳事業は市町村レベルの「地域生活支援事業」であるという位置づけもあっという間に決まってしまった。
手話通訳の利用に自己負担を求めるかどうかは市町村の判断に委ねられた。一方で手話通訳者の身分をどのように位置づけるかはほとんど議論のないまま法案は通過し、「手話通訳で食べていける」環境の整備は遠のいたように思う。茨城のような大都市近郊の県でさえ市町村レベルで手話通訳者をパートでなく雇うことはまず不可能に近いだろう。中学生や高校生が「将来、手話通訳者になりたい」と思えるような『職業としての手話通訳者制度』はほぼ絶望的な状況になったのではないかと思う。
そうは言っても、法案が通った以上、できた制度を少しでも良くしていこうという運動に取り組むほかない。自民党政治は「なし崩し的に」が得意だ。私たちは今こそそれを逆手にとって「なし崩し的に」障害者自立支援法を私たちの手元に引き寄せるような運動が必要だと思う。
日本手話通訳士協会の機関誌『翼』1月号には、理事の原田さんが「手話通訳事業が含まれる地域生活支援事業に関しても今後パブリックコメントが募集されます。団体としての要請活動と共に、このパブリックコメントの制度を利用して、地域の実情に根ざした要望・意見を厚生労働省に上げていくことも大切と思います。」と書かれている。
2005年をふり返ってみると、障害者自立支援法に振り回された1年だったように思う。自分でもその必要性・重要性を強く感じながら十分な勉強ができず、また周りへの訴えかけも未熟なまま終わってしまったという反省が大きい。大きな福祉制度改革の前にボランティアレベルの自分の力のなさを痛感した1年でもあったけれど、この反省記録をバネにしてこれからまた一つ一つ勉強を積み重ね、周りの仲間たちと次の一歩に向けて頑張っていこうと思っている。
| トップページに戻る | 木のつぶやきメニューに戻る |