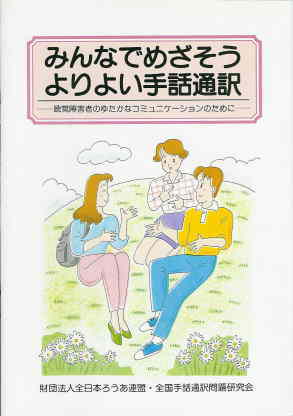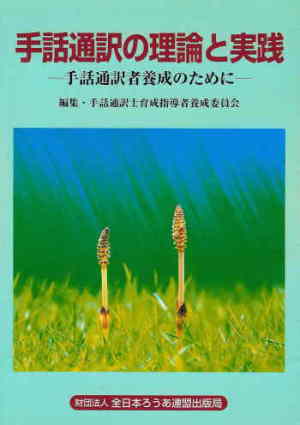 |
�@��P���@��b�ʖ�_�`��b�ʖ�җ{���̂��߂Ɂ` �@��P�́@��b�ʖ�w�K�̗��_�Ǝ��� �@�@�P�D�͂��߂Ɂ|��b�ʖ�w�K�̌��� �@�@�@(1)��b�ʖ�җ{���̕��݂ƌ��� �@�@�@(2)��b�ʖ�w�K���_�̍\�z�̕K�v�� �@�@�@(3)�u��b�ʖ�ҁv��ڎw���l�X�̎�b�ʖ�w�K�̗v���Ɖۑ� �@�@�Q�D��b�ʖ�Z�p�w�K�Ƃ́|���̗��_�ƕ��@ �@�@�@(1)��b�ʖ�Z�p�Ƃ� �@�@�@(2)���Z�p�̌n�Ƃ��Ă̎�b�ʖ�Z�p �@�@�R�D��b�ʖ�w�K�̓W�J�|��b�ʖ�җ{���R�[�X�̍\�� �@�@�@(1)�Ȃɂ��ǂ̂悤�Ɋw�Ԃ̂��|��b�ʖ�җ{���R�[�X�̍\���ƖڕW �@�@�@(2)�e�L�X�g�A���ނ̍\���ƖڕW �@�@�@(3)�w�K�҂̐S���܂��Ɗw�K���� �@��Q�́@��b�ʖ�w�K�i�g���[�j���O�j �@�@�P�D�\���Z�p �@�@�@(1)����܂ł̕]�����@�@31 �@�@�@(2)�ʖ�Z�p�̂V�̃`�F�b�N�|�C���g�Ɏ������o�� �@�@�@(3)�V�|�C���g�Ƃ� �@�@�Q�D�|��Z�p �@�@�@(1)�|��Z�p�Ƃ� �@�@�@(2)�������Ȃ��l�̔w�i�c�� �@�@�@(3)���{��̕\���� �@�@�R�D��b�ʖ�Z�p�g���[�j���O �@�@�@(1)��b�ʖ�Z�p�g���[�j���O�Ƃ� �@�@�@(2)��b�ʖ�Z�p�g���[�j���O�̗͖@�ƖړI �@�@�S�D��b�ʖ���H�Z�p �@�@�@(1)��b�ʖ���H�Z�p�Ƃ� �@�@�T�D��b�ʖ���H�Z�p�g���[�j���O |
| �@��R�́@���o��Q�҂̕�炵�Ƃ��̎��� �@�@�P�D���o��Q�Ƃ� �@�@�@(1)�݂ȓ����ł͂Ȃ� �@�@�@(2)���A�̒�`���� �@�@�Q�D���o��Q�҂̋���Ɣ��B �@�@�@(1)�R�p�^�[���̈Ӗ�������� �@�@�@(2)������Ƃ��̕ω� �@�@�R�D�E��̍L���� �@�@�@(1)�E�Ƃ̕ϑJ �@�@�@(2)�o���̐Ϗd�˂Ɛ��U����ۏ� �@�@�@(3)�����Ԃ̏��� �@�@�S�D���̕�炵�Ə��ۏ� �@�@�@(1)�m�[�}���C�[�[�V���� �@�@�@(2)�����̋ߑ㉻ �@�@�T�D���o��Q�Җ��Ǝ�b�ʖ� �@�@�@(1)�Љ�I���Ƃ��� �@�@�@(2)����낤���Җ��̍\�} �@��S�́@��b�ʖO�ƋƖ� �@�@�P�D��b�ʖ�_�̕��� �@�@�@(1)�u��b�̂ł��镟���i�v�̐ݒu�v������u�낤���҂̌���������b�ʖ�v �@�@�@(2)�낤�^���̍��܂�Ǝ�b�ʖ�֘A���Ƃ̊J�n �@�@�@(3)�낤���҂̌���������b�ʖ�҂���Љ�I���R�̊l���ւ̋��͎҂� �@�@�Q�D��b�ʖ�҂̋Ɩ� �@�@�@(1)�u��b�ʖ�Ɩ��w�j�쐬�ψ���i1987�N�j�v�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�E�� �@�@�@(2)��b�ʖ�ւ̎Љ�I�v�����猩���b�ʖ�҂̋Ɩ����� �@�@�@(3)���o��Q�҂̑w�̈Ⴂ���痈���b�ʖ�Ɩ� �@��T�́@��b�ʖ�Ǝ�b�ʖ���H �@�@�P�D��b�ʖ���H�̎��� �@�@�@(1)��b�ʖ���H�ɂ��� �@�@�@(2)��b�ʖ���H�̎��_ �@�@�@(3)��b�ʖ���H�̉ߒ� �@�@�Q�D��b�ʖ�J���̔��W������� �@�@�@(1)��b�ʖ�J���̐�含�ɂ��� �@�@�@(2)��b�ʖ�҂ɂ��Ƃ߂���\�� �@�@�@(3)�n��̒ʖ�͂Ɠo�^��b�ʖ�҂̖��� �i��P���@���M�S���� �@�@��P�́@�с@�q���i�O�d�Z����w�����Ȋw�ȏ������j �@�@��Q�́@�s��b���q�i�S����b�ʖ��茤����j �@�@��R�́@�ɓ�貗S�i�S����b�ʖ��茤����j �@�@��S�́@�Ό��Ύ��i���{��b�ʖ�m����j �@�@��T�́@�ߓ��K��i�Љ���@�l�E���s���o�����Q�ҕ�������j |
�@��Q���@��b�ʖ_�̔��W�Ɍ����� �@�@��P�́@��b����w�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O�ێq�i�L���Z�p�Ȋw��w�H�w���������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���M�s�i�R�w�@��w���ې����o�ϊw�������j �@�@�P�D����Ƃ͉��� �@�@�Q�D��b�Ƃ͂ǂ�Ȍ��ꂩ �@�@�@(1)���{��b�̒P��̂Ȃ肽�� �@�@�@(2)�ʑ����Ɯ��Ӑ� �@�@�@(3)��b����Ɖ�������̕\���P�� �@�@�R�D��b��b�̊g�� �@�@�@(1)��b��b�̉��ǁA�V���Ɋւ����{���j �@�@�@(2)�u�V������b�v�̑���@ �@�@�@(3)�����̖��_ �@�@�S�D���Ƃς̑��l�� �@�@�@(1)���Ƃ̕ώ� �@�@�@(2)�W���� �@�@�T�D��b�Ɣ�R�~���j�P�[�V���� �@�@�@(1)��b�Ɗ�̕\�� �@�@�@(2)�p�� �@�@�U�D�܂Ƃ� �@��Q�́@�����I��b�ʖ�_ �@�@�@�@�@�@�@�@���{���s�i���c�@�l�S���{�W���A�������ǒ��j �@�@�͂��߂� �@�@�P�D��b�ʖ�̗��O�Ǝ�b�ʖ�҂̂���� �@�@�@(1)���o��Q�҂̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ��̔w�i �@�@�@(2)����`���� �@�@�@(3)�ʖ�̈���L���� �@�@�@(4)�������z���� �@�@�@(5)���{�l�E���{��E���� �@�@�Q�D��b�ʖ�̍\���ƒʖ�Z�p �@�@�@(1)���b�Z�[�W�̈Ӑ}������ �@�@�@(2)�\�� �@�@�@(3)��b�ʖ�҂͐l�Ȃ� �@�@�R�D��b�ʖ���H�ɂ������� �@�@�@(1)���O���� �@�@�@(2)�₢�Ԃ��̔��f�ƕ��@ �@�@�@(3)��b�\���̌^�E����Ɛ��� �@��R�́@��b�ʖ��@�̊J�� �@�@�@�@�@�|��b�ʖ�җ{���R�[�X�ɂ�����w���@�E�]���@�̌�����ʂ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�ђq���i�O�d�Z����w�����Ȋw�ȏ������j �@�@�P�D��b�ʖ�җ{���R�[�X�ɂ�����w���Z�p �@�@�@(1)�{���u���ɂ�����u�t�̐� �@�@�@(2)���Z�u�t�̖����Ǝw���Z�p �@�@�@(3)���Z�u�t�̎����ƍu�t�{�� �@�@�Q�D��b�ʖ�җ{���R�[�X�ɂ�����]���@ �@�@�@(1)��u�ґI��̂��߂̕]���i��u�ґI�莎���j �@�@�@(2)�{���u���w���ɂ������u�ҕ]�� �@�@�@(3)�{���u���I�����ɂ����铞�B�x�]�� �@�@�R�D���W�I�Ȋw�K�@�Ǝw���@ �@�@�@(1)�芈�ʖ�җ{���R�[�X�̐��ʂƉۑ� �@�@�@(2)��蔭�W�I�Ȏ�b�ʖ�ҁi�m�j�{���̓W�J�Ɍ����� �@��S�́@���E�̎�b�ʖ�җ{���̌��� �@�@�@�@�@�@�@�@�A���p���i���{�Љ�Ƒ�w�Љ�ƌ������������j �@�@�P�D�͂��߂� �@�@�Q�D���E�e���̎�b�ʖ�җ{�� �@�@�@(1)�A�����J���O�� �@�@�@(2)�x���M�[ �@�@�@(3)�f���}�[�N �@�@�@(4)�C�M���X �@�@�@(5)�t�B�������h �@�@�@(6)�t�����X �@�@�@(7)�h�C�c �@�@�@(8)�M���V�� �@�@�@(9)�A�C�������h �@�@�@(10)�C�^���A �@�@�@(11)�X�y�C�� �@�@�@(12)�X�C�X �@�@�@(13)�X�E�F�[�f�� �@�@�R�D�܂Ƃ� |