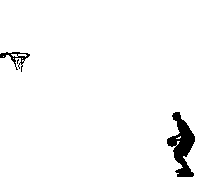|
1.久しぶりに手話サークルたんぽぽ(世田谷区)に参加した。ネットで見たら今日は講演会で、白川富子さんが「たんぽぽ創設時の思い出」というテーマでお話しをするとのこと。僕もそのころの話しはあまり聞いたことがなかったので是非と思い三軒茶屋に足を運んだ。大勢の新しいメンバーを前にしての話しで、白川さんも多少遠慮されたのか、あまり細かい話しは伺えなかったが、これまで話しに聞いていた創立当時の出来事に、実際の固有名詞が加わって、何か生き生きと記憶が蘇ってくるような錯覚を覚えた。当然、僕はその頃、まだ手話に出会っていなかったので、「記憶」であるはずはないのだけれど、10年誌や20年誌で何度も読んだ「たんぽぽ創設当時のお話し」を改めて生き証人からお話しを伺うことができ、とても良かった。是非、記録をキチンと残したいものだ。歴史に学ぶというのは、どのような運動にとっても大切な振り返りだと思う。過去を検証し、その経験を踏まえて前に進もうとするからこそ、新しい未来を築けるのだと思う。
2.参議院選挙が公示された。25日に選挙区候補者政見放送の日程が決まったそうです。すでに最初の29日の放送は終わっていて、ガックシです。
参院選茨城選挙区立候補者の政見放送の放送開始日時は次のとおり。
【NHK総合テレビ】
6月29日午前6時半と午後1時5分
【テレビ朝日】
7月2日午前5時
→すでに29日のNHKは見落としてしまった。7月2日は必ず見なければ…。
【NHKラジオ第1】
6月29日午前7時20分と午後0時半
【茨城放送】
6月27日午前9時半
7月2日午後10時20分
7月6日午後10時20分(以上、毎日新聞より)
3.手話サークルが成熟化するに伴って、サークルでも若い世代と年配者とのバランスに心がけなければならなくなっていると思う。今日、たんぽぽに参加したら以前からのメンバーTさんが4月に退会したとのこと。この件については、改めてキチンと考えてみたい。
|
![]()