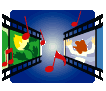
| 木のつぶやき | 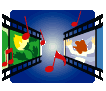 |
| 2003年3月19日(水) |
無力感といかに戦うか!
今回のイラク攻撃に対して、色々な方がいろいろな形でメッセージを発信しています。
<1>パウロ・コエーリョ(ブラジルの作家)のメッセージ
朝日新聞夕刊9面の「文化」のコーナーにパウロ・コエーリョさんの「ありがとう、ブッシュ大統領」私たちを無視し、反対者を除け者にし、無力感といかに戦うかを教えてくれて。とのメッセージが掲載されました。
<2>イギリスのクック院内総務、対イラク武力行使に抗議して辞任
| ■英閣僚辞任:クック院内総務辞任 対イラク武力行使に抗議 3月18日 01:49 |
|
ブレア英政権の主要閣僚の一人、クック枢密院議長兼下院院内総務(前外相)が17日、辞任した。同院内総務は国連決議無しの米英主導の対イラク武力行使に反対していた。抗議の辞任とみられる。 |
日本の大臣は、こんな時にも存在感ないよなぁ〜。農水大臣なんて、まるで低次元な理由で国会空転させてるもんなぁ〜。
<3>度を越す米には直言を−田原総一朗氏
3月16日の朝日新聞19面に「三者三論−緊迫するイラク情勢」ということで与那原 恵さん(ノンフィクションライター)、クライン孝子さん(ノンフィクション作家)と共に意見を書かれていた。
「日本の立場の弱さは承知の上だが、米国が国連無視の戦争を始めたら、日本政府はせめて米国の行為に対し遺憾表明ぐらいは明確に打ち出すべきである。」
「そして、米国の武力行使は、あくまで国連決議687号、1441号に基づくものであり、目的はイラクの大量破壊兵器の破壊であって、フセイン政権の打倒やフセイン封殺などは全く目的外で、大勢のイラク国民を殺傷する権利などないことを、米国にしっかりと念押しすべきである。」
<4>決議欠く攻撃「国際法違反」 研究者ら声明提出へ
3月18日(火)朝日新聞2面及び4面に、次のような記事が載りました。
日本の国際法研究者が「イラク問題に関する声明」をまとめ、近く外務省に提出する。国連安全保障理事会の新たな決議なしの武力攻撃は国際法上違法とし、「力による支配ではなく、法による支配を強化して国際平和を確保するには、国連を育んでいくほかに道はない」と訴える。
声明は、大沼保昭東大教授、古川照美法政大教授、松井芳郎名大教授が国内の研究者約40人に賛同を呼びかけた。「武力の行使と武力による威嚇」は国連憲章によって禁止されており、例外的に認められるのは自衛権の行使か、平和に対する脅威や破壊に対する集団的措置として安保理が決定する行動に限られる、と指摘。今回の武力行使はいずれにも当たらないとしている。
古川教授は「国際法研究者が共有している意見を表明し、社会に知ってもらうことが大事だと考えた。イラク問題を考える際の基準にしてほしい」と話している。
日本の国際法学者らがまとめた「イラク問題に関する国際法研究者の声明」の要旨は…こちら。
<5>日米韓協調に亀裂の展開も−チャールズ・カプチャン氏(ジョージタウン大学準教授・国際関係論)
3月19日(水)朝日新聞より(下線は木下)
ブッシュ政権は国際社会に別れを告げて、独自の道を歩もうとしている。大統領は単独行動主義に基づき、同盟国との協調関係よりも、イラクを攻撃して得られる安全の方が優先すると判断した。
この判断は誤っている。多くの国が米国のリーダーシップへの拒否反応を抱き、世界を分断しかねない危険をはらむ。
国連が受けた痛手は大きい。安保理で支持を得られないと見た米国が、国連の腕をへし折って出てきたも同然で、すぐには立ち直れないだろう。
欧州は、戦後に平和維持軍を送ることはもちろん、戦後復興への参加にも消極的になるはずだ。「米国が壊したのだから、米国が立て直せばいい」ということだ。
これまでのような米欧協調関係は終わりを告げる。北大西洋条約機構(NATO)も戦略的で実質的な意味をもった組織としては続かない。
指導者間で個人的な憎悪も生まれており、米大統領、独首相、仏大統領が政権にいる間は、各国の関係が冷え込むはずだ。
北朝鮮は「イラクの次は自分たちか」と考える可能性がある。
将来の朝鮮半島危機では小泉首相がブレア英首相の役を演じ、はやる米国を抑えようとする韓国は、廬武鉉大統領がシラク大統領の役を演じる。
その結果、日米韓の協調関係にひびが入ることも考えられる。
(聞き手・和泉聡=ワシントン)
<6>李 鍾元(リー・ジョンウォン)立教大学教授(国際政治)に聞く
3月19日(水)朝日新聞15面「イラク攻撃を問う」・・・ちょっと長文ですが、これまでのアメリカの態度の問題点が分かりやすく指摘されていると思います。(下線は木下)
問−イラクに最後通告を突きつけた米国の選択をめぐって、国際世論は大きく割れています。
「最後通告に至る国際社会でのせめぎ合いには『国際秩序をめぐる闘い』という性格があったと私は見ています。自らを頂点とする『帝国』的な新しい国際秩序を構築しようとする米国と、それに抵抗する勢力との闘いです。」
問−ブッシュ政権のどこが「帝国」的だと。
「国連と国際世論が反対し、国際法に抵触する恐れが強くても、米国は単独の意思で戦争をすることができる、と主張していることです」
問−17日の大統領の演説にも「帝国」の論理は表れていますか。
「米国は従来の国際法に縛られない、と宣言した演説だと思う。『米国は、自国の安全保障のために武力を行使する主権を有する』と、今回の武力行使を自衛権に基づくものとして正当化しようとしている。
しかし、正当な自衛権の行使には、事態の緊急性や脅威と手段との釣り合いなどが求められる。今回のイラクにこれをあてはめるのは拡大解釈としか言いようがない」
問−攻撃回避の条件としてフセイン大統領らの国外退去を挙げました。
「戦争の目的を『イラクの政権交代』と明確に示したものです。しかし、ある国の政治体制を標的にした軍事行動がかろうじて認められるケースは、他国を侵略した場合と自国内で大量虐殺など重大な人権侵害が現在行われている場合だけです。イラクは、そのどちらでもない」
問−独裁者が主権の論理で守られていいのかという批判もあります。
「私も『国外にいる者は何もしない』ことを支持するのではない。しかし、武力行使で政権を変えようとするなら、少なくとも一定の条件が要ります。
今回の『戦争』は、従来の国際法の体系に照らして緊急性が薄い。米国内には、ヒトラーや大日本帝国を例にして攻撃を正当化する議論もあるが、ヒトラーや日本は当時侵略をしていた。またユーゴ空爆のときには、実際に虐殺がありました」
問−今回米国を批判した勢力は、どんな原理に立っていたのでしょう。
「基本的には、帝国的な国際秩序の構築はおかしい、という考え方に依拠していたと思います。冷戦の終了後、グローバル化に対応して、国際秩序に関する二つの考え方が浮上した。
一つは、国境を超えた問題に対処するため国際社会の多様性を認めながら協調していこうという考え方。
もう一つは、多様性によって安全がおびやかされているとして、国境を閉ざして安全を守ろうとする考え方です。後者の傾向は各国に見られますが、顕著に表れているのが今の米国です」
問−国際協調をどこまで重要と考えるか、その違いでしょうか。
「人類はこの500年近い歴史の中で、主権国家の体系を作り上げてきました。そこでは、国家同士は対等だという『国際関係における民主化』が目指された。武力行使にルールをかけようという国際法的な実践も積み重ねられた。 しかし、戦争はなくならなかった。
その反省に立って、国家単位では対処できない問題に各国が共通して対処しようと作られたのが国連です。米国がもしこのまま戦争をすれば、国連システムを根幹から否定することになる」
問−新しい国連決議が必要かどうかをめぐっても議論が割れました。
「従来の決議は、武力行使を正当化するものとは言えない。『米国の自衛権だ』という主張だけでなく、従来の決議で十分という主張を盛り込んだのは、日本を始めとする各国が協力できる根拠を提供したかったからでしょう」
問−米国が武力行使をちらつかせたから、イラクが査察にある程度協力した、という見方もあります。
「経済制裁や査察が効果をあげていないという主張はあるが、イラクではいまだに核兵器が見つかっていないし、大量破壊兵器が存在する明白な証拠も出ていない。過去に侵略した事実はあるが、この10年ない。これらは、湾岸戦争後の10年間に実行された国際的な制裁や査察が効果を上げていることの証拠だとも言えるでしょう」
問−日本は早々と米国支持を表明しました。
「日本としては、無条件な対米支持を打ち出すより、国際社会の諸原則を踏まえた議論をするべきだったと思う。無条件の追随は危うい。原則を持っていなければ、国連での存在感を示すことができなくなってしまいます」
「日本、韓国は、世論は反米なのに、政府は米国支持です。反米といわれる廬武鉉政権でさえ、工兵部隊の派兵を約束した。狭い国益を考え、米国に協力せざるを得ない状況が浮き彫りになっている」
問−悲観的な要素しかないのでしょうか。
「反戦世論や安保理での議論をみて感じるのは、新たな国際秩序の萌芽です。想像以上にその基盤ができつつある。思わぬ副産物です。チリとかアンゴラは帝国的秩序よりも、それに代わる秩序を望みました。いまは国連システムを守るべきだと判断したわけです。しかし、こうした動きは東アジアでは弱かった」
問−国連はどうなっていくのでしょう。
「今回の戦争が国連システムに打撃を与えるのは確かです。そもそも国連は戦争をむやみにしないというのが大原則ですが、それを一番大きな国が、おおっぴらにやるのですから。
でも、国連の出番はまだある。戦争が泥沼化した時などです。せっかく生まれた国際世論をベースに、国連を中心とする体制を強化する必要があります。そのダイナミクスが生まれる可能性はあります。欧州が地域としてまとまって新しい秩序を求める動きも出てくるでしょう」
<7>各国の態度表明−「米支持」表明30カ国にとどまる。
3月19日(水)朝日新聞夕刊より
米支持、30カ国にとどまる 日本には戦後復興支援期待
ブッシュ米大統領がイラクに突きつけた最後通告の期限切れまで1日と迫った18日、湾岸に展開する米英軍28万5千人は攻撃へ最終態勢を整えた。
ブッシュ政権は、立ち遅れた外交包囲網の構築に全力を尽くした。
パウエル米国務長官は米国支持を表明した国のリストを発表したが日本、英国、韓国、オーストラリアなど30カ国にとどまった。
支持の内容は派兵から基地の提供、領土領空の通過、復興支援などにわたる。
91年の湾岸戦争では、国連決議に基づいた武力行使だった上に、多国籍軍参加国だけでアラブ諸国も含めて28カ国を数えたことに比べ、支持の薄さが際立つ結果となった。
パウエル国務長官は記者団に対して「米国を支持するリストに含まれることを公にした『有志連合』は30カ国に及ぶ。様々な理由で公表は望まないが、米国を支持する国がさらに15カ国ある」と述べた。長官はまた、「強い指導者だけが、世論の反対にもかかわらず危険を理解し、このような問題に取り組む重要性を認識している」と述べ、米支持を表明した各国の指導者に謝意を示した。
支持を表明した30カ国の内訳をみると、冷戦終結で米国に恩恵を受けた東欧及び旧ソ連諸国が突出して多く13カ国。ラムズフェルド国防長官が「古い欧州」と呼んだドイツ、フランスは加わらず、米国の隣国のカナダやメキシコも含まれていない。湾岸戦争ではシリア、エジプトなどアラブ諸国も多国籍軍に参加したが、今回は、アラブからの支持はなかった。
日本については、バウチャー国務省報道官が会見で、日本を特に名指しして、軍事行動ではなくイラクの戦後復興で協力すると発表した。
AP通信によると、米国以外は、英国が4万5千人、オーストラリアが2千人、ポーランドが200人の兵力提供を表明したほか、アルバニアが非戦闘要員として70人、ルーマニアが地雷除去や生物・化学兵器の汚染除去、憲兵隊要員などに278人を提供する。
<対イラク戦争で米国支持を表明した30カ国>
(国務省発表、アルファベット順)(下線・太字=兵力提供国は木下)
アフガニスタン、アルバニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、コロンビア、チェコ、デンマーク、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、グルジア、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、韓国、ラトビア、リトアニア、マケドニア、オランダ、ニカラグア、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スペイン、トルコ、英国、ウズベキスタン
<8>「イラク反戦」516議会採択−全国自治体 本社まとめ
2月から3月の定例議会で米軍などによるイラク攻撃に反対する決議や意見書を可決した地方議会が少なくとも全国47都道府県の517議会にのぼることが18日、朝日新聞社のまとめで分かった。
緊迫してくるイラク情勢を受け、採決日を早めた議会もある。残る会期で採決を予定している議会も多く、今後さらに増えそうだ。
18日までに可決したのは、都道府県議会レベルでは全国の半数を超える26議会。市町村議会では491議会。
イラクに大量破壊兵器の廃棄を要求する一方で、「市民が被害を受けることのないよう、武力行使は回避させなければならない」(北海道議会)などと求める内容が大半だ。
採決日を早めた議会もある。
鳥取県倉吉市議会は当初、今月20日の3月議会最終日に採決する予定だったが、「イラク情勢の切迫」を理由に急きょ14日に繰り上げた。その際、意見書案をまとめる準備が間に合わないなどの理由で、前日に可決された鳥取市議会の意見書を取り寄せて内容をそのまま借りるほど、急いで可決した。
2月議会で「平和的解決」を求める意見書を可決した山梨県議会は、事前の総務委員会では同様の趣旨の市民団体からの請願を「採決留保」にしていた。攻撃準備を進める米国を支持する小泉政権に自民党県議団が配慮したのがきっかけだったが、その後、各地方議会で自民党が同調したうえで反戦決議が可決されていることを知り、態度を一変させた。
「国が方針を決めていない段階でとやかく言うべきではない」(愛媛県議会2月定例会)などと否決した議会もある。
米軍などによるイラク攻撃の可能性が浮上してきた昨年9月から年末にかけて可決した地方議会は、朝日新聞社の集計では、「イラク攻撃」と明示して反対したものだけで72議会にのぼった。
2月と3月議会では「イラク攻撃」と明示せず、一般的な戦争反対を唱えるものも含まれているが、イラク攻撃の可能性が高まったことが反戦決議や意見書の可決急増の背景にあるとみられる。
■2月、3月議会でイラク反戦の決議・意見書を可決した地方議会数(○は道府県議会が可決)
北海道 28 ○
青 森 1 ○
岩 手 18 ○
秋 田 28 ○
山 形 3 ○
宮 城 14
福 島 45
茨 城 4
東 京 18
神奈川 14 ○
千 葉 6 ○
埼 玉 19
群 馬 4
栃 木 1
山 梨 5 ○
静 岡 1
長 野 52 ○
新 潟 13
富 山 1 ○
石 川 3 ○
福 井 2
愛 知 13 ○
岐 阜 17
三 重 11 ○
大 阪 12 ○
京 都 14
兵 庫 11 ○
滋 賀 8 ○
奈 良 11 ○
和歌山 8 ○
岡 山 3
広 島 13
鳥 取 12 ○
島 根 3
山 口 8 ○
香 川 4
徳 島 3 ○
愛 媛 8
高 知 19
福 岡 4
大 分 3
佐 賀 7 ○
長 崎 6 ○
熊 本 3 ○
宮 崎 2
鹿児島 5 ○
沖 縄 29 ○
計 517 (18日現在) (03/19 13:46)
世の中まだまだ捨てたもんじゃない。20日午前10時まで、あと8時間。やれることをやろう! 無力感などクソくらえ! なんとしても、アメリカのイラク攻撃をストップさせよう!
| トップページに戻る | 木のつぶやきメニューに戻る |