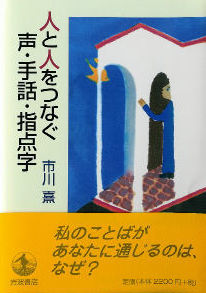
慶應義塾大学工学部卒。1964年、日立製作所入社。同社中央研究所主任研究員を経て、現在、千葉大学大学院自然科学研究科教授。専門は音声言語処理と福祉情報工学。先端情報技術を障害者支援技術に応用するために、1999年に「福祉情報工学研究会」を設立。また、情報通信機器を障害者にも使いやすくするために、現在、関係省庁や業界団体と協力して、その標準化に取り組んでいる。
| タイトル | 人と人をつなぐ声・手話・指点字 | 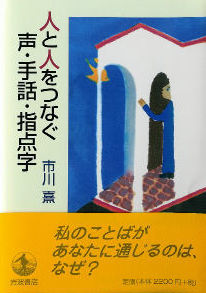 |
| 著者 | 市川 薫(しばた たけし) | |
| 1941年生まれ。 慶應義塾大学工学部卒。1964年、日立製作所入社。同社中央研究所主任研究員を経て、現在、千葉大学大学院自然科学研究科教授。専門は音声言語処理と福祉情報工学。先端情報技術を障害者支援技術に応用するために、1999年に「福祉情報工学研究会」を設立。また、情報通信機器を障害者にも使いやすくするために、現在、関係省庁や業界団体と協力して、その標準化に取り組んでいる。 |
||
| 出版社 | 岩波書店 | |
| 発行日 | 2001年(平成13年)10月19日発行 | |
| 読了日 | 2004年8月16日(月) | |
| 価格 | 2,200円+税 |
本の内容(Amazon.comで買うなら… )
表紙裏より…
「手話や、左右三本ずつの指を使う指点字は、声のことばと同じように、考えていること感じたことを自由に表現できる手段だ。生き生きとした会話を支える秘密はプロソディ・・・文字にすると消えてしまう抑揚やリズムが想像以上に活躍している。もっと豊かなコミュニケーション実現のために、福祉の世界でプロソディに注目した工学者の挑戦。」
も く じ
もくじ 抜き書き 頁 1 豊かなコミュニケーション それにしても、声に限らず手話や指点字で、かくも豊かに会話ができるのはなぜなのでしょうか。本書では、その秘密の一端を探ってみたいと思っています。 5 2 手話との出会い 声の高さや、大きさ、リズムなどは、「プロソディ」とよばれます。日本語では、韻律とか抑揚など、いろいろに訳されていますが、本書では以降プロソディとよんでいくことにします。アクセントやイントネーションなどとよばれるものもプロソディの仲間です。
プロソディは、一つ一つの音にではなく、一連の音に対して付けられる現象を指します。たとえば、アクセントでは、/ア/、/メ/の一つ一つの音に対してではなく、それが連なった/アメ/ということぱ全休での声の高さの変化で「雨」と「飴」が区別されますね。喜怒哀楽も全体の声の調子で、その感情が表されます。
手話の動作の大きさや速さも、この音声のプロソディと同じような働きをもっているのではないでしょうか。私は、これを手話のプロソディとよびたいと思います。
(中略)
話は戻りますが、というようなわけで、このトロント大学での手話の実験が、音声研究者としての私が、プロソディを手掛かりに福祉の分野でなんらかの貢献ができるのでは、という自信を与えてくれたものでもあり、そのーつとして表現力豊かな手話の工学的研究を始めようと考えたきっかけともなったものなのです。10 3 手話とはどんな言語か ・禁じられていた言語
・言語障害と手話
・言語の獲得
・「なぜ私たちから手話を奪うのか!」
・メディアとコード
4 「市川さんの実験はもういや」 ・音声タイプライタができたから
・HAL2000−音声対話をするコンピュータ
・自然な対話音声を集める。
・不要語?
・あいづち
・言いなおし、言いよどみ、共話
・文とは
・話し手の交替
・誤解の効用
5 声の仕組み ・声の構造
・RとL
・なぜ歌えるのか
・濁った音
・高い声、低い声
・男の声、女の声
・声を作る
・コンピュータが声を認識するとは
・ことばの意味を理解する6 話しことばと書きことば ・ガーデンパス文と音声
・音声のプロソディ
・プロソディの持つ情報
「・・・プロソディには、音声による文を構成している『単語間の意味の関わり合い情報』が存在しているらしいのです。」
・「・・・どうぞ」
「・・・コミュニケーションの主導権は、かなりの部分が聞き手にあると考えても良さそうです。」
・漫才とニュース
・文字で歪んだ言語観
「・・・書きことばでは、なぜ完成までにいろいろと修正を加え文章を整えなければ意図が伝わらないのか、逆に話しことばではそんなにしなくても、なぜコミュニケーションができるのだろうか、ということです。」
・文字で進んだ言語研究
・文字のないことば7 しゃべる指 ・盲聾者との出会い
・盲聾者(視聴覚重複障害者)とは
・切実なコミュニケーション
・長野でのできごと
・ここにも「あいづち」
・盲聾者のコミュニケーション手段
・「私たちのためにも考えてください」
・今なぜ指点字なのか8 ことばのリズム ・音声のリズム
・音声対話のリズム
・手話のリズム
・ことばの三点角
・メトロノーム手話
「音声に三角点が付けられるならば、手話に付けることはできないものでしょうか。それができれば、手話の時間構造を測る基準点が決められ、リズムなども正確に調べることが期待できますね。」
・手話文の構造
・指点字のリズム
・指点字と文の構造
・「ぽっぽっぽ、はとぽっぽ」
・「こんなに面白い話しがあるのね」
・言語の処理と脳
「・・対話のことばに対する重要な視点の一つは、受けとる立場にとって、送り手の情報が、まさに同時に実時間で理解できる構成になっているらしいということだと思います。
そこには、三つの視点があると考えています。第一点は、なんらかの共通の場が形成されるような仕組みがある、第二点は、受け手が瞬時に理解するために、送り手の出す信号には意味の単位をまとめたり、その単位の間の関係を示したりする情報が存在しているということです。第三点は送り手と受け手の間で情報のやりとりのためのきっかけとなるなんらかの仕掛けがあるらしい、ということです。」9 情報技術者がみる夢 ・手話教育と手話のリズム
「・・・手話の勉強も、日本手話のリズムにもとづいた体操のようなものを工夫し、ラジオ体操のようにその体操をサークル活動のはじめに毎回したらどうなのかな」
・手話の通訳システム
・視覚障害者もホームページが読める
・盲ろう者のための電話、放送受信機、読書機、インターネットブラウザ
・「独り言」をいうコンピュータ
![]() 読後感
読後感
| トップページへ戻る | 書籍CONTENTSへ戻る |