−ことばのしくみを考える
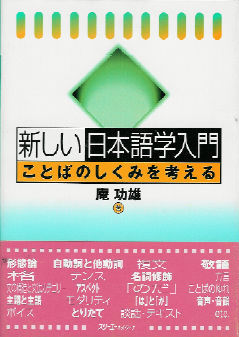
| タイトル | 新しい日本語学入門 −ことばのしくみを考える |
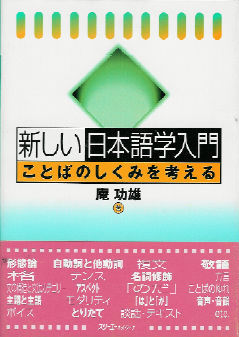 |
| 著者 | 庵 功雄(いおり いさお) | |
| 出版社 | スリーエーネットワーク | |
| 発行日 | 2001年(平成13年)2月26日発行 | |
| 読了日 | 2004年1月(購読中)日(未定) | |
| 価格 | 1,800円+税(税込み1,890円) |
本の内容(Amazon.comで買うなら… )
<本書帯書きより>
1.日本語の文法を中心に、音声・音韻、形態、敬語、方言にわたって最新の研究成果を紹介。
2.日本語学で用いられる専門用語について丁寧に解説。
3.「モー娘。」はなんと読む? 「このピラフ全然おいしいよ」などの楽しいコラムも満載。
<本書「まえがき」より>
まえがき
本書は現代日本語を材料にことばに関する研究(言語学)の考え方を理解していただくことを目的に執筆したものです。
ことばはヒトを他の動物と区別する最大の特徴だと言えます(→§1)。
従って、ことはのしくみを知ることは究極的には人間とは何かということを知ることにつながることになるはずです。
言語学の研究はさまざまな角度から行えますが、本書では統語論を中心に、できるだけ多様な切り□を紹介することに努めました。本書の題名は「新しい日本語学入門」ですが、「はじめに」にもあるように、「日本語学」は現代日本語に関する言語学的考察を総称する用語です。
「日本語は特殊だ」と言われることがあります。でも、本当にそうでしょうか。「特殊だ」と言われる日本語の基本語順は実は世界の言語の中で最も多いタイプのものなのです(→コラム5)。一方、授受表現で「やる・あげる」に当たる動詞と「くれる」に当たる動詞を区別する言語は非常に珍しいです(→§9)。このように、日本語の中にも特殊なものと一般的なものがあります。大切なのは「特殊だ」「一般的だ|ということを「日本語の事実に即して」考えることです。本書を通して、母語である日本語のしくみを客観的に考える方法を知っていただければと思います。
本書をお読みいただく上で前提となる知識は必要ではありません。新しい用語がたくさん出てきますが、それらは全て本書の中で定義されています。
本書は現代日本語を研究しようとする学部生・大学院生だけではなく、言語学の学生、さらには日本語(ことば)のしくみについて考えようとする全ての方を対象に書かれたものです。
本書は1999年に一橋大学留学生センターから『一橋大学留学生センター教育研究シリーズ2 ことばのしくみを考える』として出版されたものを大幅に加筆修正したものです。本書の出版に当たって、出版の申請を快く了解してくださった一橋大学留学生センターの各位に心よりお礼申し上げます。最愛の妻佳子、つぐみ(ミニレッキス)と暮らす国立にて 2001年1月 庵 功雄
も く じ
ちょっと長いのですが、索引としても使えるほど(ちゃんと巻末に正式な索引も付いてますが…)丁寧な目次なので、全文ご紹介します。
まえがき
凡例
はじめに
§1 言語学の1分野としての日本語学
1.ヒトのことばの特徴
1−1.二重分節
2.現代言語学とソシュール
2−1.言語記号の恣意性と社会性
2−2.ラングとパロール
2−3.共時言語学と通時言語学
3.文法の役割
4.文法の生得性
5.まとめ
コラム1「モー娘。」は何と読む?
§2 音声・音韻
1.音声(パロールとしての音声)
1−1.母音
1−2.子音
2.音素(ラングとしての音声)
2−1.相補分布
2−2.有標と無標
3.音声と音素−ローマ字の表記−
4.アクセント
4−1.アクセントの地方差
4−2.東京式アクセントの特徴
5.イントネーション
6.プロミネンス
7.まとめ
<資料1>
§3 形態論(1)−形態素、語、品詞−
1.形態素とは
2.語とは
3.品詞
3−1.主要部と修飾部
3−2.品詞の決め方
4.まとめ
§4 形態論(2)−活用−
1.活用とは
名詞の活用
2.学校文法の活用表
学校文法
3.理想の活用表を求めて
3−1.活用(表)に関わる基本概念
語幹と語基
3−2.理想の活用表に必要なこと
3−3.理想の活用表に必要な活用形
3−4.活用の種類と活用表(動詞)
3−5.活用の種類と活用表(形容詞)
4.まとめ
コラム2「バーティーは楽しいでした。」
§5 格
1.格とは
格の表し方
2.必須補語と副次補語
3.表層格と深層格
表層構造と深層構造
格表示のもう一つのパターン
4.格枠組みの機能
5.まとめ
§6 文の構造と文法カテゴリー
1.日本語の文の構造
2.文法カテゴリー
2−1.文法カテゴリーの取り出し
カテゴリーの表示の義務性
2−2.辞書形の位置づけ
3.単語の意味と文法的性質の関係
3−1.単語の意味と文法カテゴリー
3−1−1.肯否、丁寧さ、対事的モダリティ
3−1−2.ボイス
3−1−3.アスペクト
3−1−4.テンス
3−1−5.対人的モダリティ
4.まとめ
§7 主題と主語
1.主語とは何か
2.三上章の主語廃止論
2−1.主題
2−2.無題化
三上が主張したかったこと
3.柴谷方良の主語プロトタイプ論
3−1.再帰代名詞「自分」とその先行詞
3−2.尊敬語化
3−3.主語プロトタイプ論
4.まとめ
§8 ボイス(1)−受身と使役−
1.ボイスとは
2.受身
2−1.直接受身とは
面接受身と他動性
2−2.間接受身とは
2−3.中間的な受身
2−4.受身の機能
3.使役
3−1.使役文の構造
3−2.使役文と格
4.受身、使役の生成文法による分析
5.まとめ
§9 ボイス(2)−授受−
1.授受表現とは
2.語彙的ボイスとしての授受動詞
3.視点とは
「視点」に敏感な日本語
4.授受動詞の対立の仕組み
4−1.「やる/あげる」と「くれる」
4−2.「やる/あげる」・「くれる」と「もらう」
日本語の授受動詞の特殊性
5.授受動詞における人称
6.恩恵の授受
7.授受動詞の全国分布
8.まとめ
コラム3 「スリーエーネットワークがどこですか。」
§10 自動詞と他動詞
1.自動詞・他動詞と自他の対応
自他の対応のパターン
自動詞・他動詞と意志性
2.所動詞と能動詞
三上の動詞分類と非対格性の仮説
3.自動詞文の機能
4.自動詞・他動詞と受身・使役
4−1.受動文と自動詞
動作主の説焦点化
4−2.使役文と他動詞
5.まとめ
コラム4「二十歳を過ぎるとお肌のお手入れも大変だわ。」
§11 時間を表す表現(1)−テンス−
1.ル形、夕形、テイル形
異形態
2.テンスとは
3.テンスから見た述語の分類
4.タ形の意味
5.2種類の過去
6.従属節の中のタ形とル形
7.まとめ
§12 時間を表す表現(2)−アスペクト−
1.アスペクトとは
2.テイル形の意味
2−1.テイル形の基本的な意味(継続)
方言におけるアスペクト
2−2.テイル形の派生的な意味(経験・記録、完了)
2−2−1.経験・記録
2−2−2.完了
3.テンスとアスペクトの関係
4.アスペクトとテキスト
5.まとめ
§13 モダリティ
1.モダリティとは
2.対事的モダリティ
2−1.当為的モダリティ
2−2.認識的モダリティ
2−2−1.断定
2−2−2.推量
2−2−3.可能性
2−2−4.確信
2−2−5.証拠
2−2−6.兆候
3.モダリティと疑問、否定
3−1.モダリティと疑問
3−2.モダリティと否定
4.対人的モダリティ
5.「だろう(か)」について
6.まとめ
§14 とりたて
1.とりたて(る)とは
2.とりたて助詞の統語的性質
3.とりたて助詞の意味の記述
4.範列的関係と統合的関係
5.とりたて助詞としての「は」
6.まとめ
コラム5 オランウータンは森の人
§15 複文(1)−単文と複文−
1.英文法における文の分類
2.日本語における複文の定義を求めて
2−1.三上章の分類
2−2.南不二男の分類
2−2−1.A類、B類、C類、D類
2−2−2.A類〜D類の相互関係
2−2−3.南の構造が意味するもの
3.まとめ
§16 複文(2)−因果関係−
1.因果関係を表す複文
2.論理文の体系
3.条件
3−1.仮定条件
論理記号
誘導推論
3−2.反事実的条件
3−3.確定条件
3−4.恒常的条件
3−5.事実的条件
3−6.条件を表さない「〜と」「〜たら」
4.原因・理由
4−1.出来事の原因・理由
4−2.判断の理由(根拠)
4−3.「から」と「ので」
5.譲歩・逆接
5−1.条件文の否定とは
5−2.譲歩と逆接
5−3.「のに」と「けど」
6.まとめ
コラム6 「これ、全然おいしいよ。」
§17 名詞修飾
1.修飾の2つの種類
2.2つの名詞修飾節
3.内の関係
制限的修飾と非制限的修飾
3−1.主名詞になれる名詞の格
格の階層
3−2.関係代名詞の機能
格助詞がない場合
4.名詞修飾と陳述度
5.外の関係
6.益岡隆志による修正
7.まとめ
§18 「のだ」
1.疑問文と否定文における「のだ」
1−1.疑問文と「のだ」
1−2.否定文と「のだ」
2.開連づけの「のだ」
関述づけを表す「からだ」と「わけだ」
3.認識のあり方に関わる「のだ」
4.他の言語における「のだj
文法化
5.まとめ
文献紹介1
§19 「は」と「か」
1.1は」と「が|の使い分けに関わる要因
1−1.文の陳述度と主題
「は」と対比
1−2.有題文と無題文
1−3.指定文と指定文
2.「は」と「が」の便い分けと情報の新旧
3.他の言語回折における」は」と「が」
4.まとめ
§20 談話・テキスト
1.テキスト
2.結束性
3テキストレベルの文法現象
3−1.話し手・聞き手の知識と「という」の有無
3−2.指示詞
3−2−1.現場指示と文脈指示
3−2−2.ソとア
情報のなわばり理論
3−2−3.コとソ
4.機能主義的研究
4−1.省略
4−2.後置文
5.文体
6.その他の研究
7.まとめ
§21 敬語
1.待遇表現としての敬語
2.敬語の分類
3.尊敬語
4.謙譲語
5.丁寧語
6.授受動詞の敬語形
7.丁寧語
8.美化語
9.敬語における人称
10.ウチとソト
11.素材敬語から対者敬語へ
12.敬語の機能
13.まとめ
§22 方言
1.方言に関するさまざまな研究法
2.方言地理学
2−1.柳田国男と方現周圏論
2−2.糸魚川調査
3.社会言語学的研究
4.文法体系の比較
5.まとめ
§23 さまざまなバリエーション
1.ことばのゆれ
1−1.ラ抜きことば
規範文法と記述文法
1−2.「〜が…たい」と「〜を…たい」
2.「〜と、〜ば、〜たら」
3.「違かった」など
新方言とneo-dialect
4.まとめ
文献紹介2
コラム7「パパ、日曜だからってゴロゴロしないで。」
あとがき
![]() 読後感
読後感
| トップページへ戻る | 書籍CONTENTSへ戻る |