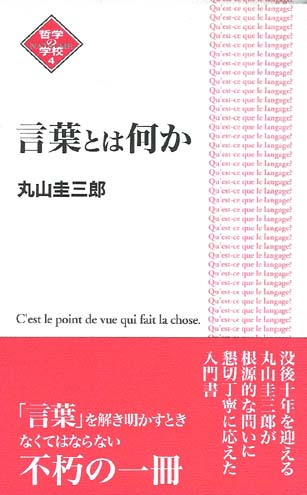
| タイトル | 言葉とは何か | 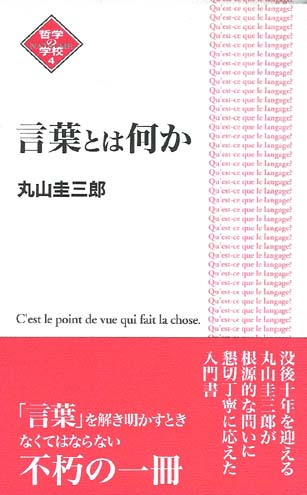 |
| 著者 | 丸山 圭三郎(まるやま けいざぶろう) | |
| 出版社 | 夏目書房 | |
| 発行日 | 2001年4月25日 改訂新版第1刷発行 | |
| 読了日 | 2002年 | |
| 価格 | 1,700円+税 |
![]()
本の内容
(下線は木下)
●「私たちの生活している世界は、言葉を知る以前からきちんと区分され、分類化されているのではありません。単語のもつ音の価値も、意味の価値も、その言語の体系のなかだけで決定されるのであり、言葉が、あらかじめ区切られた独立の存在である物や概念の名前でないということは、多くの実例が証明しています。のちにもくわしく見るように、言語を構成する諸要素は、その共存それ自体によって互いに価値を決定しあっているのです。概念は言葉とともに誕生し、それぞれの単語は全体の体系のなかにおかれてはじめて意味をもち、その大きさ、意味範囲はその単語を取り巻く他の単語によってしか決められません。極端な例をあげれば、日本語から「狼」という単語が時代を経て使われなくなるや否や、狼と呼ばれていた動物は「犬」という概念に包摂されてしまうでしょう。
(帯に引用されていた本文10頁「1.言葉と文化」)」
○…ところが、翻訳作業はまことに困難を極めました。ただ単語を置きかえていくなどという仕事でないことは覚悟していたそうですが、文法上の問題以上に彼らを悩ましたのは文化そのものの違いだったのです。たとえば、かぐや姫が歌ってヒットした「神田川」をマレー語に訳したマレーシアの留学生には、まず「風呂屋」という語が翻訳不可能であったし、「同棲」は母国では恥ずべき行為。まして「洗い髪が芯まで冷え、小さな石鹸がカタカタ鳴る」まで待たされた女が、「あなたのやさしさが怖かった」などと言うその心情は、マレーシア人には到底納得できなかったと言っています。
最も基本的なことから考えてみましょう。言葉は音声で表されるとしても、この音声はいわゆる叫び声とかうめき声とは違っています。私たちが胃痛を覚えた時、「ウーン」とうめいて他人に苦痛を訴えることもできますが、このうめき声は区切りのない音声で苦痛を表現しているばかりか、それがはたして頭痛なのか歯痛なのか胃痛なのか区別できません。ところが「イガ イタム」という言葉を使用して苦痛を訴える場合は、同じ音声の連続体であっても、それぞれ区切られた音に対応する意味を理解することができます。
これは当りまえのことのようで、実は大変重要なことなのです。私たちが外国語をはじめて耳すると、ふつうは一連の雑音の波としか聞こえません。これは、私たちにとって知らない言葉はちょうどうめき声とか叫び声のように聞こえ、どこでどう区切られ、それぞれの区切りがどんな意味をになっているかがわからないからです。フランス語を全く知らない人にzemalalestcma!(木下注;一部の発音記号が正しく表示できていません)という声の連続体を聞かせた場合を想像してください。zem/al/al/…と区切るのかze/mal/a…と区切るのか、一切見当もつきません。外国語を学習するということは、まず、この音の連続体をどのように区切って不連続体として受けとるかという能力を身につけることなのです。
(本文14頁)
木下;聴者が、手話の動きを「見切る」(微妙な手話の変化や手話の区切りを見分ける)ことができないことと同じだと思いませんか?
○ところで、この区切り方が、日本語でもフランス語でも英語でも全く同じだとしたら話は簡単です。日本語の「犬」にあたるフランス語のcheienや英語のdogを覚えておけばよいのですから、外国語学習というのは単語の暗記だとも申せましょう。しかし、「胃が痛む」という体験を*Estomac souffre.(正しいフランス語ではありません。 文字通りには、「胃が痛む」という意味。左肩につけた*印はあり得ない形であることを示します)とは言わないところに問題があります。
これは単に構文の違いということだけではなく、私たちが世界中に共通する一定数の概念をもっていて、言葉はそれぞれ既存の概念に《名づけ》をするものではないことを意味しています。言葉は、それが話されている社会にのみ共通な、経験の固有の概念化・構造化であって、外国語を学ぶということは、すでに知っている事物や概念の新しい名前を知ることではなく、今までとは全く異なった分析やカテゴリー化の新しい視点を獲得することにほかなりません。
言語が、それ自身文化であり、思考形式であるというのも、右のような事実から言われることで、たとえばフランス語を学ぶということはとりもなおさず、全く新しいものの見方を身につけること、すでに私たちが日本語を通して知っている世界を別の観点から読解・把握することであり、日本的思考といういわば 《単眼》 に、フランス的思考を加えた 《複眼》 にし、これを通して新しい生き方を始めることなのです。
(本文15頁)
木下;これって、手話を学ぶ聴者の視点にも必要なことではないでしょうか?手話を学ぶとは、まず、「ろう文化」という視点を獲得することだと思うのです。
○すでにくわしく実例を通して見たように、言葉は、それが話されている社会にのみ共通な、経験の固有な概念化なのです。もちろん、どのような言語を用いるにせよ、それぞれの言語によって分節される概念以前の現実たとえば第1章でとりあげた虹の色とか、一日の時間の長さといったもの)が、言語の相違と関係なく、もともと同一の存在であることは疑えません。ただ、私たちがこの言語外現実を把握し、私たちを取り巻いている世界を区切り、グループ別に分け、カテゴリー化するのは、言語を通してである、ということなのです。
言葉以前の現実は混沌とした連続体であって、私たちは自国語の意味体系のおかげで、この連続体の適当な個所個所に境界線を画すことができます。ところが、言語によって意味体系が異なるのですから、言語が変れば区切り方も変ってくるのは、当然でしょう。
たとえば、「木」とか「植物」とか「動物」という一般的な、しかも抽象的な性格をもつ単語が一切存在しない言語はたくさんあります。そうした言語には、木や植物の個々の名称、たとえば「松」「桜」「杉」といった語はあるのですが、「木」という概念がないために、それらをひとまとめにしてカテゴリー化することができません。
(本文86頁)
木下;これも、手話という言語を考える時に、当てはまると思います。
![]() 読後感
読後感
| トップページへ戻る | 書籍CONTENTSへ戻る |