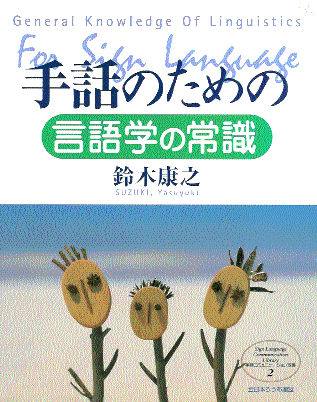
| タイトル | 手話のための言語学の常識 | 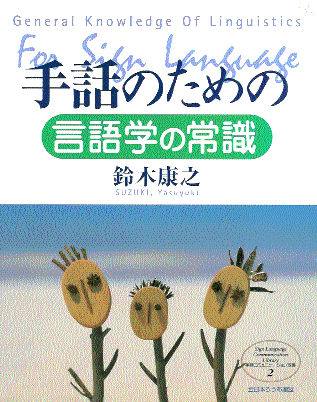 |
| 著者 | 鈴木 康之 | |
| 出版社 | 全日本ろうあ連盟 | |
| 発行日 | 2001年7月20日 初版発行 | |
| 読了日 | 2002年9月13日(金) | |
| 価格 | 2,500円+税 |
1 「話」が理解できるということ
・・・(略)・・・。
[37頁下段〜]
一般に、ことばというものは、現実をうつしだす機能をもっている。
言語活動の具体的な単位としての「文」は、くみたてのうえからみれば、ひと切れの現実を名づける単位としての「単語」をもとにしてつくられている。
単語は、現実の関係のうえからは、ひと切れの現実(現実の一部分、現実の一側面、現実に存在する部分・側面など森羅万象すべて)を名づけつつ、一方、文との関係では、文をくみたてる基本的な構成単位として機能している。
つまり、人間は、ひと切れの現実を名づける単位としての単語をくみあわせることによって、具体的な言語活動の単位である文をつくっているのである。そして、この「文」によって現実をうつしだし、さらに、いくつかの文を連ねて一まとまりの「話」をつくっているのである。
このことを通訳者という立場で考えてみよう。
具体的な言語活動としての「話」をきちんと通訳して理解させるということは、個々の「単語」を手がかりとして、個々の「文」に語られている一まとまりの姿を通訳される個々の人々の頭のなかに映像化し、さらに、文の連なりによって「話」にまとめられている複雑な一まとまりの現実(多くの場合は、時々刻々と変化している)を自分自身で具体的にイメージさせてみせるということである。
そうだとすれば、通訳者にとっては、常に、言語および言語活動の基本的な単位としての「単語」「文」を大切に扱うことが要求されることだろう。
はじめに
手話をいま学んでいる方々、手話を学びはじめたばかりの方々、さらには、これから手話を学ぼうとしている方々に、こころから声援をおくろうと思います。声援をおくるということの具体的な一つの行為として、このような著作を公刊いたしました。つまり、本書「手話のための言語学の常識」は、日本語を母語として生育された方々を対象として、手話を学ぶための土台となるような日本語についての言語学的な知識を一覧してみたというものです。
ところで、みなさまには、「手話は言語である。」ということを実感していただけるでしょうか。言語であるということは、単なる伝達の手段だということではありません。同時に、認識・思考の道具でもあるのです。手話を母語とする方々、すなわち、生まれながらに手話で生育された聴覚障害の方々は、手話で認識・思考しながら、言語としての伝達活動をしているのです。本書は、そのような事実をことのほか意識して執筆してみたというものです。
すでに社会的な活動を重ねている老練な手話通訳者でも、よく、手話は分かるが日本語が分からない、というような意味のことを口にすることがあります。実に、奇妙なことではないでしょうか。
だが、その奇妙なことにも理由があるのです。手話にかぎらず、外国語(母語でない言語)を習得するというような場合には、つねに、ことばのしくみを意識しながら習得するという思考活動が伴います。つまり、意識して学習する「手話」(外国語の一つと考えてください)は、不完全ながらも、ことばのしくみが見えているものなのです。しかし、母語は、つねに無意識・無自覚のうちに習得してきています。つまり、無意識・無自覚のうちに身につけてきた日本語は、ことばのしくみが見えにくいものなのです。
あらためて申しあげます。本書は、手話に関わる方々のために、見えにくい日本語のしくみを見えるように示してみたというものです。もちろん、理想的な姿からは縁遠いものかも知れません。しかしながら、類書が皆無であるという現状を考えてみれば、どうか、本書を有効に活用してみてください。みなさまの今後の活躍をこころから祈念申しあげます。
2001年6月 鈴 木 康 之
![]()
本の内容
<もくじ>
| はじめに | |
| 第1章 ことばのしくみと手話 1 ことばのしくみとしての語彙と文法 |
|
| 2 母語としての日本語と母語としての手話 | |
| 3 第1言語と第2言語 | |
| 4 手話ができるということ | |
| 5 ふたたび語彙と文法について | |
| 第2章 言語であるということ 1 言語の発展のすばらしさ |
|
| 2 方言の共存を言語の豊かさに | |
| 3 自由な言語活動と縛られた言語活動 | |
| 4 言語の恣意性 | |
| 5 国語教育の責任の重さ | |
| 第3章 ことばを理解するということ 1 「話」が理解できるということ |
|
| 2 ことばを意識することのむずかしさ | |
| 3 ことばによる認識・思考 | |
| 第4章 日本語の動詞の活用 1 国際的な言語学の常識と学校文法 |
|
| 2 「日本語教育」と「国語教育」 | |
| 3 生きた文法の学習のために | |
| 第5章 日本語動詞のテンスとムード 1 日本語動詞のテンスとムード |
|
| 2 現在形の用法 | |
| 3 過去形の用法 | |
| 4 断定形と推量形の用法 | |
| 5 勧誘形と命令形の用法 | |
| 第6章 日本語動詞のアスペクト 1 文法的なカテゴリーとしてのアスペクト |
|
| 2 継続相「−している」の用法 | |
| 3 結果相「−してある」の用法 | |
| 4 終結相「−してしまう」の用法 | |
| 5 アスペクトとしての「−してくる」「−していく」 | |
| 第7章 日本語動詞のボイス 1 文法的なカテゴリーとしてのボイス |
|
| 2 受動態の用法 | |
| 3 使役態の用法 | |
| 4 使役受動態の用法 | |
| 5 なぜボイスが発達してきたのか | |
| 第8章 日本語動詞のヤリモライとモクロミ 1 文法的なカテゴリーとしてのヤリモライ |
|
| 2 受益者が内部構造に存在する場合 | |
| 3 シテモライ態での意味的な関係づけ | |
| 4 受益者が内部構造に存在しない場合 | |
| 5 ヤリモライ動詞としての意味の修止 | |
| 6 ヤリモライ動詞の特殊な用法 | |
| 7 システムの原則を理解すること | |
| 8 文法的なカテゴリーとしてのモクロミ | |
| 第9章 日本語動詞の連体形と分詞形 1 動詞の基本的な言い方 |
|
| 2 動詞の連体形 | |
| 3 動詞の分詞形 | |
| 4 連体形・分詞形の特質 | |
| 第10章 文の組み立て 1 なぜ文に構造が生じるのか(主語・述語) |
|
| 2 文の構造と現実との関係(対象語・修飾語) | |
| 3 出来事の生じる時間・場所など(状況語) | |
| 4 二次的な文の成分としての規定語 | |
| 5 文の付随的な成分としての独立語 | |
| 6 文の組み立ての原則(学校文法批判) | |
| 第11章 文と節と連語 1 文の部分としての節 |
|
| 2 単純文・並列文・複合文 | |
| 3 単語の組み合わせ | |
| 4 名づけ的な単位としての連語 | |
| 5 単語に固有な連語の構造 | |
| 6 連語の構造と単語の意味 | |
| 7 文の材料としての連語 | |
| 8 一語文 | |
| 第12草 コトバによる現実の描写 1 コトバで語る複雑な現実 |
|
| 2 文学作品での描写 | |
| 3 文中に現れる作家の構想 | |
| あとがき |
![]() 読後感
読後感
<いずれ書ければいいのですが・・・>
| トップページへ戻る | 書籍CONTENTSへ戻る |