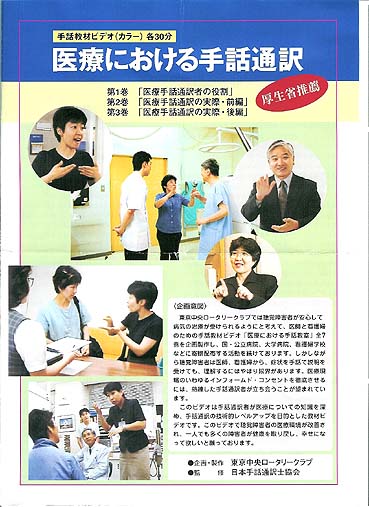2002年度茨城県手話通訳者養成講座2(応用・実践) <カリキュラム検討 第3回>
◆医療場面における手話通訳について(士協会ビデオの紹介)
・茨城県手話通訳者協会県南支会の定例学習会の1月のテーマは、「医療場面通訳」とのこと
・それで事務局から「どんな内容でやったらいい?」という問いかけがありましたので、僕は「士協会が監修した「医療における手話通訳(全3巻・各5000円)」をみんなで見て話し合いをしてはどうでしょうか?」と提案してみました。
・すかさずSさんから「ビデオを使ったらどうかと私も木下さんとおんなじ事を考えていました」との提案もありました。
・Sさんの説明では、「このビデオは昨年12月に士協会から会員に配布されたもの」で「第2巻では問題点をさり気なく盛り込んで通訳している場面が出てきます。…そして、問題点に対して士協会の会長 石原さんが解説しています。」とのこと。
・勉強会のやり方としては、「第2巻を見て問題点を話し合う。その際に<ろう者が求める良い通訳とは何か?><医療場面で通訳を受けるとき、ろう者自身はどんな準備が必要か?>などについて話し合えると良い」ですね、とのこと。
・僕も、もらった時にほんのちょっとだけ見た切りで、今回初めて3巻全てを「ざっと」見てみました。(「じっくり」見ている時間がないので…)
・ところがこれが実に素晴らしいビデオなんです。特に2巻・3巻は実際の通訳場面を見ながら石原さんがあれこれ解説してくれます。僕は3巻目の方が、よくできるなぁ〜と思いました。
(1)第2巻ビデオを見る(30分)
(2)第2巻ビデオに対する質問や話し合い(30分)
(3)第3巻ビデオを見る(30分)
(4)第3巻ビデオに対する質問や話し合い(30分)
・こんな感じで学習会をやってはどうかな?
手話教材ビデオ 「医療における手話通訳」 (カラー)各30分
第1巻 「医療手話通訳者の役割」(27分)
第2巻 「医療手話通訳の実際・前編」(30分)
第3巻 「医療手話通訳の実際・後編」(30分)
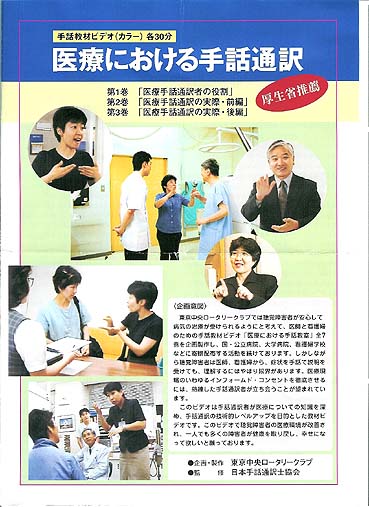
[お問い合わせ]
東京中央ロータリークラブ
〒104-0061東京都中央区銀座8‐11‐12正金ビル2F
TEL 03‐3573‐2653 FAX 03‐3289‐1100
E-mail:chuo2750@mint.ocn.ne.ip
日本手話通訳士協会
〒170-0013東京都豊島区東池袋4‐27‐5ライオンズプラザ池袋201
TEL 03‐5953-5882 FAX 03‐5953‐5883
E-mail:aaa11890@pop06.odn.ne.jp
|
<各巻の内容>
第1巻 「医療手話通訳者の役割」 (27分)
・病院での不安な体験を語る聴覚障害者
・特別養護老人ホーム「いこいの村・梅の木寮」(京都府)の紹介
・開所当時、診断書とは異なる深刻な病気が多くの入所書から発見された
・入所者の病院での体験談
・梅の木寮での医療説明の工夫
・梅の木寮所長、大矢暹さんのお話
・市立四日市病院で正規職員として働く手話通訳者・蒔田一美さんの紹介
・診察室での通訳風景
・レントゲン室での聴覚障害者への配慮
・院内手話サークルの活動
・日本で初めて聴覚障害者外来が設置された琵琶湖病院(滋賀県)の紹介
・手話で対応する受付スタッフ
・聴覚障害者外来担当医師・藤田先生のお話
・病院スタッフによる手話学習会
・「いこいの村・梅の木寮」の盲ろう重複障害者と大矢所長とのコミュニケーション風景
第2巻 「医療手話通訳の実際・前編」 30分
・障害者スポーツ文化センター・横浜ラポールにある聴覚障害者情報提供施設での手話通訳派遣業の紹介
・通訳派遣担当・平井正子さんのお話
・手話通訳の実際・中途失聴者Aさんの場合(解説:石原茂樹さん)
・待ち合わせ・初診受付・問診票の記入
・診察室・次回予約をめぐって
・手話通訳の実際・主に手話で思考するろうあ者Bさんの場合(解説:石原茂樹さん)
・問診票の記入・診察室・レントゲン撮影室
・検査の不安への対応
第3巻 「医療手話通訳の実際・後編」 30分
・手話通訳の実際・主に生活体験の範囲で思考するろうあ者Cさんの場合(解説:石原茂樹さん)
・受診相談受付・初診申込用紙への記入・問診票への記入・診察室・独自の手話表現をめぐって・薬局
・報告書について
・京都市聴覚言語障害センター副所長・近藤幸一さんのお話・横浜ラポール通訳派遣担当・平井正子さんのお話
・まとめ |
|
推 薦 : 厚生省
企画・製作 : 東京中央ロータリークラブ
監 修 : 日本手話通訳士協会
製作担当 : 株式会社 東文 |
<企画意図>
東京中央ロータリークラブでは聴覚障害者が安心して病気の治療が受けられるようにと考えて、医師と看護婦のための手話教材ビデオ「医療における手話教室」全7巻を企画製作し、国・公立病院、大学病院、看護婦学校などに寄贈配布する活動を続けております。しかしながら聴覚障害者は医師、看護婦から、症状を手話で説明を受けても、理解するにはやはり限界があります。医療現場のいわゆるインフォームド・コンセントを徹底させるには、熟練した手話通訳者が立ち会うことが望まれています。
このビデオは手話通訳者が医療についての知識を深め、手話通訳の技術的レベルアップを目的とした教材ビデオです。このビデオで聴覚障害者の医療環境が改善され、一人でも多くの障害者が健康を取り戻し、幸せになって欲しいと願っております。
<ビデオ解説 −日本手話通訳者協会会長 石原茂樹>
医療場面における手話通訳
1 はじめに
このビデオ教材は、医療場面における手話通訳のあり方に一定の方向性を示し、問題提起をしてはいますが、いわゆる「マニュアル」のためのビデオではないことを、まずご理解下さい。
どのような専門技術でも、その理念や原理が大事でありますし、それらを正確に学習していれば、現場での応用がきくものです。
日本の手話通訳者は、「伊東論文」(昭和43年/1968年)や「安藤・高田論文」(昭和51年/1976年)に掲げられた崇高な「手話通訳理念」をもってきました。また、日本手話通訳士協会は、「倫理綱領」(平成9年/1997年)も持つに至っています。理念と同時に大切な現場での技術論については、全国手話通訳問題研究会の中に、「手話通訳活動あり方検討委員会」という恒常的な研究組織を設け、そこで、手話通訳実践についての集団的な検証と理論化がすすめられています。
このビデオ教材は、そうした日本の手話通訳者が構築してきた、理念や技術論の流れの中に位置し、それらの更なる発展を願って作成されました。私たちが扱う手話という言語は、三次元とも四次元ともいわれる文法をもち、きわめて映像的です。ビデオ教材の存在価値は、そこにあると信じています。どうか、全国の手話通訳士が、それぞれの地域において、あるべき医療場面の手話通訳像の更なる構築に、この教材をフルに活用下さることを願ってやみません。
2 健康=基本的人権
世界保健機構(WHO)の保健大憲章によれば、「健康とは、単に疾病があるとかないとかというだけにとどまらず、身体的にも精神的にも、そしてまた社会的にも良い状態をいう」としています。さらにこの大綱には、「そして、この健康の確立を図ることは、すべての国にとって、もっとも大切な義務であり、かつ健康はあらゆる人々にとって、その社会的条件、政治的信条、宗教的区別、人種などにかかわりなく達成されなければならない生まれながらの権利である」とも書かれています。
国際人権規約(1966年)の「A規約」12条は、「健康を享受する権利」になっていますが、そこには、「この規約の締結国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める」としています。
つまり、健康であることは、間違いなく人間がもつ権利なのです。そして、常に、最高水準の健康を求めることもまた、国際的に認められた権利なのです。
しかし、聴覚障害者はこれまでどのような医療を受けてきたでしょうか。このビデオの冒頭に、数人の聴覚障害者の生の声を収録してありますが、過去には、コミュニケーションが通じないために手後れになり死亡された聴覚障害者もあり、大きな社会問題にもなったこともあります。
私たちは、そうした背景や歴史をきちんと見据え、今後は、聴覚障害者が主人公となれるような医療を築いていきたいものです。
3 私たちのもつ専門性
インフォームド・コンセントは、通常、「説明と同意」と訳されていますが、「びわこクリニック」の藤田保先生は、「理解と選択」であると主張されています。つまり、自分の理解できることばで、納得できるまで説明を聞き、選択肢を示してもらい、そして拒否も含めて自分で選択をしていくことを保障するという取り組みであり、権利なのです。
しかし、手話通訳者が、相手に理解できない手話やコミュニケーション方法で伝達しようとしたら、どうなるでしょうか? せっかく、医療スタッフがインフォームド・コンセントを大切にして、病状と治療方針について説明しても、入り口のところで、壊してしまうことになります。
手話通訳者は、目の前にいる聴覚障害者のニーズに合わせたコミュニケーション方法の選択ができなければなりません。このビデオでは、何人かの聴覚障害者に登場していただき、それぞれの方に対して、どのようなコミュニケーション方法が最善なのかを学習していただきます。
ところで、通訳という業務は、言語の異なる人の間に立ち、コミュニケーションを仲介していく業務です。音声言語の通訳者の世界では、「ランゲージ・スペシャリスト」と「コミュニケーション・スペシャリスト」の2タイプの通訳者像があるとされています。手話通訳の場合は、どうでしょう、たくさんの経験を出し合っていく中で、実は、聴障者のコミュニケーション力によって、私たちが自然と、ランゲージ・スペシャリストになったり、コミュニケーション・スペシャリストになったりしていることに気付きます。言葉をかえて言うならば、聴障者が主体的に判断しているのです。私たちは、この両極の通訳像を意識して、「聴障者のコミュニケーション力や周囲との関係などを総合的に見て、この両極の間のどのあたりでの通訳を行うべきか、的確に判断していかなければならないのです。
4 医療スタッフとの協働
三重県の四日市市立病院で、手話通訳を行っている方を、第1巻で紹介していますが、登録手話通訳者として派遣されていく通訳者と、医療スタッフとして位置づけられている手話通訳者とでは、おのずと通訳業務の幅や深さに違いが出ます。
これまでは、それはやむを得ないものと考えられてきたのですが、今後は、登録派遣というスタイルであっても、必要な場合には、医療スタッフの一員として位置づけられるような手話通訳像が求められてくるでしょう。
その際に重要なことは、手話通訳者自身が、各医療スタッフの業務内容や役割を理解することと同時に、手話通訳者の視点での聴障者の観察や援助はどのようにあるべきかということについての合意をどう作るかということです。この協働を実のあるものにするには、担当する手話通訳者が、医療というものをよく理解し、聴障患者の状態を科学的に観察し、その状態を、周囲のスタッフに的確に伝えるための技術をもつことが必要です。
5 まとめ
WHOは、人々が健康であるための必須条件として、「健康でありたいと願う気持」をあげています。第1巻で「いこいの村」に入所されている方たちのさまざまな証言、職員たちの創意工夫された実践の紹介、そして大矢所長の語りは、何度観ても、私たちの胸をうちます。コミュニケーションに関わる者としての責務は、私たち自身も「健康であってほしい」と心から願い、そして、決してあきらめないということであることを、おしえてくれています。
なお、医療場面の手話通訳と言うと、病気になってかちのことのみを考えがちでずが、もっと広い視野で考えるべきです。このビデオでは紹介できませんでしたが、兵庫県での「いのちを考えるつどい」や、京都の「患者会作り」の実践など、予防の領域まで広げ、取り組んでいる地域がたくさんあります。こうした実践からもっともっと学び、全国各地で、医療関係者も交えての実践が展開されるようになってほしいと考えています。
<養成講座メニューに戻る> <トップページに戻る>